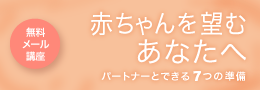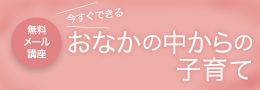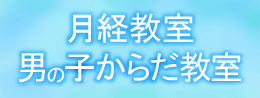ブログ
2021年02月26日
3歳児で入園した◯くんは
ちょっとしたトラブルで
とっさに
友だちを噛んでしまう。
幼稚園の先生が
一人貼り付き
パッと止められるように
して新年度スタート
それでも止められず
ママは、
友だちとそのママに
謝る日々でした。
噛み付く子は
ここを愉氣すると解決
という急所があると
山上亮先生の本にあり
ママは
藁にも縋る思いで
講座に参加しました。
先生に直接
ママと◯くんのからだも
みてもらい
ママにできることを
すぐに実行。
しばらくして
気がついてみると
あれ?いつの間にか
噛み付かなくなっている!
「こんな平和な日々が
来るとは!夢のようです」
とママは振り返ります。
2〜3歳の
子どもの噛みつき。
言葉では効果なく
からだの手当で解決できる
方法があるのでした。
[季節に合わせた整体生活]
晴・夏・秋・冬
春3月からスタートします!
2021年01月13日
<寒の季節>
寒さが厳しくなっていること
日々実感していることと思います。
暦の上では
一年を二十四等分に区切った
「二十四節気(にじゅうしせっき)」では
2021年の1月5日に
二十三節気の「小寒(しょうかん)」
19日の「大寒(だいかん)」を合わせ
立春を迎える前日(節分)までの
30日間を
「寒の内(かんのうち)」と呼びます。
寒が終わるのが「節分」
翌日は「立春」です。
ところで、明日の日の出の時刻を
ご存知ですか?
本日13日の東京の日の出時刻が
6時51分でした。
東京は日本の中で早いんです。
(日本各地の日の出時刻
スマホでも
調べればすぐにわかりますよ)
この一年で一番遅い
日の出の時刻が
ここ1ヶ月ほとんど
変わりませんでしたが
今日からは少しづつ
夜明けが早くなっていきます。
夜明けを味わいたいなら、
今なら6時半でも大丈夫!
おおざっぱに言うと
日の出の約30分前が夜明けですから。

今からは日足が伸びる時。
鳥たちはそれを感じています。
私たち人間も
朝の光を浴びて
地球の上の一生物であることを
感じましょう。
世の中は1年前とは
すっかり様変わりしました。
この状態と長く付き合っていくことに
なるかもしれません。
まずは自分の時間を整えることから。
自分にできることから
始めましょうね。
浅井あきよ・記
2020年11月27日
クリスマスは知らない人はいませんが
アドベントはそこまで知られてはいませんね。
クリスマス前の4回の日曜日は
待降祭『アドベント』と言って
ヨーロッパなどキリスト教文化圏では
<「クリスマス=誕生=降誕」を待つ> という日です。

毎年、日付は変わりますが
12月25日前の4回の日曜日が
第一〜第四アドベントとして
祝われます。
今年は11月29日(日)が
第一アドベントですね。
アドベントカレンダーと言って
一日づつ窓を開けると
中から小さなお楽しみが出る
というのもあります。
あと何日と
毎日、日数数えて待つという
この体験は子ども心に
ワクワクするものでしょう。
私がこの「アドベント」を初めて知ったのは
2000年の11月に
ドイツのニュルンベルクで開かれた
シュタイナー教育の研修会に参加
したときでした。
園長の仕事を3週間も離れて
賢治の学校主催の研修会に
参加したのです。
ちょうど、その時期
ニュルンベルクは恒例の
クリスマスマーケットが
開かれていました。
研修に参加しているのは
全員日本人で
講義は現地の先生がドイツ語で行ない
すべてに日本語通訳が付いていました。
アドベントの飾りとして
モミの木と赤いリボンで飾られた
大きな4本の蝋燭を立てたものがあり
1週間ごとに蝋燭に火をつけていくのです。

日の暮れは早く
日の出は8時くらいで
毎朝、朝食の時は
外が真っ暗な中でしたので
蝋燭がきれいだな、と思ったのを
覚えています。
アドベントの季節になると
この時のことを思い出します。
これだけ夜が長いと
冬至を境に、日が伸びるのを
心待ちにする気持ちがよくわかります。
心待ちにする気持ち
これが、この時期の気持ちなのだと思います。
元々あった冬至を祝う光の祭りと
イエスの誕生を祝うクリスマスが
結びついた、という説もあります。

日本のお正月も
冬至とほぼイコールですね。
ちょうど、この季節は
新しいカレンダーが出たり
来年の手帳やダイヤリーが
売り出される時期です。
冬至へ向かって
締めくくりと来年の準備を
始める時です。
一年間をふりかえり
新しい年に願いをこめる
大切な時期。
その一つの行動として
心を込めて「手帳」を選びましょうね。
アドベントから始まって
オチは手帳でした。
2020年10月12日
「胎児は見ている」の著者
トマス・バーニー博士と
池川先生との対談や講演があります。
コロナの影響でバーニー博士は
来日できなくなりましたが
代わりに
オンラインでの
トマス・バーニー博士と
池川明先生との対談
と講演が
2020年11月15日
実現することになりました。

でも
11月15日に予定を入れていて残念!
と思った方
オンライン講演会は
その後10日間限定で録画を
視聴することができます。
バーニー博士は80代です。
この機会をお見逃しなく
↓
最先端の科学と胎児の心理学を語る トマス・バーニー博士 &池川明博士 講演会
日 程:2020年11月15日(日)
時 間:13:00開場 13:30 ~ 17:00
講師:池川明博士&トマス・バーニー博士
料金:通常:\ 5,000 ⇒早割価格 \4,000 (税込)
お申込みはこちらから↓
https://www.trt33.jp/verny11/
(早割は10月15日まで)
浅井あきよ・記

2020年10月04日

山上亮先生の骨盤講座をオンラインとリアルで
参加できる講座をお願いしまして、昨日1回目開催することができました。
zoomの設定が上手くいかず、参加者の方にご迷惑をおかけしましたが、
無事に開催させていただくことができました。
野口整体的な考えのほか
学びのロマン
形態学的にみた骨盤についてのお話しは
山上先生からしか学べない
リズムとエネルギーを感じる時間でした
今後も学びの時間を創っていこうと考えております。
お話しの中で話題になった
山上かさね先生のぬか袋
(かさね先生は山上先生の奥様です)

こちらのサイトでご購入いただけます。
https://nukabukuro.base.shop/?fbclid=IwAR1UDwVX_r9ilepRXUVzHXzGjpNtiqc5sPAjWGimctiD_bpMgyj4BSoJ93Q
季節も秋本番に向かっていますので
ぜひ冷えた体をあたためるぬか袋を生活の中でもご活用ください。
そして、とくに
仙骨を温めることがおすすめです。
今後も女性と骨盤についてのお話しを
深めていこうと思います。
2020年06月05日
赤ちゃんに名前をつける時、
いろいろ悩みますよね。
幸せな悩みだとおもうけど。
多くの人は
漢字の画数とか
意味から考えるけど、
まったく別のところに注目して、
名前について考察することもできる。
それをこの黒川伊保子さんは行なっている。
耳に響く音、
でもないんだって。
口の中を通る空気の速度や舌の動きなど、
なんだって。
物理学専攻でロボット言語の研究者という経歴のこの人の考え方
とってもおもしろい。
おこられやすい名前とか、叱るつもりがほっとゆるむ名前とか、
実例がいっぱい。
ちなみに著者の伊保子という名は、
ほ という音が「ほーっ」とさせてしまい、
叱る気がほわっと消えてしまう名前だとか。

たしかに「こら!勝子!」というのとだいぶちがうな。
ご紹介した二冊は、へその緒文庫にございます。貸し出しもしていますよ。
浅井あきよ・記
2020年05月06日
こんにちは
へその緒の会の浅井あきよ です。
このところ、コロナの影響で
リモートワークで目が疲れている方、
実際に集まれないから
オンライン〇〇で
動画など画面をみることが
増えた方など
知らず知らずに目を
酷使している方は多いのでは?
今も役に立つと思いますので
ここに載せました。
目の疲れをとる〇〇〇
〇〇〇にはいる文字は「温湿布」
このところ、
毎日私は 長い時間
パソコンの前で仕事していて
夜になると、もうダメ!
というくらい眼が疲れてしまいます。
そこで、眼の疲れをとるという、
<眼の温湿布>をしてみました。
やり方は簡単
蒸しタオルを作って目をつぶって
瞼の上から温湿布。
冷めたら、
もう一度お湯で絞って当てて9分。
椅子に座ってでも
仰向けに寝て目に当てるのでもOK。
熱ちっ!というほどでなく
「ほどよい温かさ」がいいのです。
そしてずっと温かいままでなく
一度冷めてからまた温めるのがいいのです。
実際にやる前は
「冷たいタオルの方が気持ちいいのでは?」
と思っていたのですが
やってみると、
温湿布は
とても気持ちいいのです。
そして、
目だけでなく全身の疲れが取れます。
目が疲れたな!と思う時
ぜひ一度試して見てくださいね。
目と骨盤
このやり方は野口整体の先生から習いました。
目を酷使すると
骨盤の動き(開閉)が悪くなるそうです。
骨盤と言えば
お産や月経と関係が深く
月経の時は骨盤が開きます。
開きがつかえると
月経痛はじめ色々なトラブルの原因になります。
日頃、目を使いすぎている方
原因はわからないが、
月経の前に調子が悪い方
この、目の温湿布を試してみませんか?
(浅井あきよ・記)
2020年03月13日
「自然治癒力学校」(理事長・おのころ心平)
日常セラピーというメルマガがあります。
わたしも執筆者の一人として
ほぼ月一回書いているのですが
こちらに私の書いた3月12日の記事を引用しますね。
妊婦さんの役に立ってほしい、という願いから
書いています。
この、不安になるニュースの多い中で
妊婦の方が今すぐにできることを紹介しますね。
という書き出しです。
以下引用です。
◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇
その一つは、散歩をすること。
━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇赤ちゃんのための散歩◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━
誰かと歩くのではなく
(おなかの赤ちゃんといっしょにいる事を感じつつ)
一人で歩く事
買い物のついででもなく
荷物も持たず
赤ちゃんといっしょに(つまり一人で)歩く事
これは野口整体の野口晴哉先生流の
妊婦さんが赤ちゃんのためにするといいこと
です。
野口晴哉先生が言う
もう一つの大事なことは、、、、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇おなかの赤ちゃんに話しかける◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そう、
「おなかの赤ちゃんに話しかけること」
を勧めています。
おなかの赤ちゃんと二人連れで
散歩に出かけたら
両方いっぺんにできますね。
声に出して言わなくても大丈夫です。
そうすると
「それは胎教ってことですね」
と言う人がいて、そんなとき
野口晴哉先生は
「いや胎教とは私は言わない。
胎教というと
、、、、すべし
、、、、すべからず
だと皆んな思っている。
それは
おなかの子どもを萎縮させ
お産も重くさせてしまう。
私はただ生まれる前から
おなかの赤ちゃんの人格を認めて
話の通じる人間がここにいる
と思って話しかけること
日々を過ごすことを
勧めているだけなのだ」
と言ったそうです。
そしてお産が自然に進むためにも
アレをしてはダメ、
コレをしてはダメを出来るだけなくして
妊婦自身の自由を大事にすること
何より一番身近な亭主は、
自分の欲求よりも
全ては赤ちゃんのためと
妊婦を尊重するように
と今から70年以上も前に言ったのです。
ご自身もそれを実行していたことは
奥さんの野口昭子さんが
後にエッセイの中で書いています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇Have to ではなく Want toで ◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━
私たちは、コレがいいということを聞くと
つい”Have to”にしてしまいがちです。
散歩がいいんだって!が
散歩しなくっちゃ!となると
これがツライ。
かえって、できないんです。
それよりも
軽い気持ちで、
「そうか!じゃ散歩してみよ
って、するほうができます。
一回やってみて
あ、気持ちがいいな、また行こう
と思ったら
行けばいいんです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇何分歩くかは赤ちゃんと相談して◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「散歩は何分くらいが
よろしいのでしょうか」
と聞かれると、野口先生は
「赤ちゃんと相談してきめたら良いでしょう」
と言って、決して何分とは
答えなかったということです。
赤ちゃんに聞いて、ではなく
赤ちゃんと「相談して」というところに
ちゃんと妊婦さんの主体性も入っていますね。
赤ちゃんの言い分を聞くことは
自分自身のからだの声を聴くことと
ほぼイコール
同じ線上にあります。
頭がいっぱいだと
からだの声に耳を傾けられません。
野口晴哉先生は「ポカンとする」ことが大事
といいましたがその「ポカンとする=頭をやすませる」ができない人が
現代はさらに増えています。
わたしの
おなかの中からの子育てレッスンでは
たった3分でもできる
頭をやすませ、からだの声を聞くイメージワークを
レッスンの中で行なっています。散歩ができなくても
これはお部屋の中でできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇妊娠中の影響は大だからこそ◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今妊娠している人や
身近に妊婦さんのいる人は
今の時期の大切さに目を向けて
世の中のニュースなどをきいて
不安で
心をいっぱいにしてしまうのではなく
赤ちゃんへのポジティブな思いで
心を満たしましょう。
そのための
切り替えができますよ。産まれるまでの数ヶ月
人生の中ではほんの一瞬
それを知っているか知らないか
実行するかしないかで
生まれてくる子ども(とその母)の人生に
大きな影響を及ぼす
おなかの中からの子育てレッスン。
そのレッスンに関心がある方へ
ただいま期間限定で
個別相談を受け付けています。
お問合わせも、申込みも
こちらからどうぞ。
おなかの中からの子育てレッスンについて詳しくは
■おのころ心平と
一般社団法人自然治癒力学校
2020年03月11日
今年も3月11日がやってきた。
あれから満9年たったが対応策は進んでいるのだろうか?
もしもの時に一番に守るべき人たちは、未来をつくる子どもたちとおなかの赤ちゃん。胎児とママが一心同体であるだけでなく、小さな子どもとママも一緒でなければ子どもを守ったことにはならない。
………………

もし、災害が起こったら、一番に保護される必要のあるのは誰?
赤ちゃんや幼い子(と母)そして妊娠中の女性だと思う。乳飲み子を守るにはお母さんといっしょでないと無理だし、幼い子供も母といっしょにいてこそ安全、安心にすごせる。
そして何より妊娠中の人は最優先で大事にされる。
そんな先進例が、ここにある。それぞれの区や市で、これが当たり前になるように、できることを、それぞれの場所でやっていこう。
====================
災害時に妊産婦・乳児の命を守る施設
【文京区のプロジェクト~妊産婦・乳児救護所】
男女協働・子ども家庭支援センター課長
男女協働・子ども家庭支援センター課長 鈴木秀洋さん
2013年、文京区は地域防災計画に、「妊産婦」と「乳児」専用の救護所を盛り込みました。
災害時に職員及び助産師を派遣し、妊産婦・乳児の心身をケアする拠点とする取組みです。設置の経緯と、クリアしなくてはならなかった問題などについて、
設置の当時、文京区危機管理課長で、現在は、男女協働・子ども家庭支援センター課長の鈴木秀洋さんにお話しを伺いました。
東日本大震災の現場から得た教訓
「母子救護所」の必要性を感じられたのはなぜですか?
鈴木さん:2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。
震災後、先遣隊(危機管理課長)として釜石に入り、避難所の様子を目の当たりにしました。
特に妊産婦さんや、乳児の安全安心が守られていないことに、ショックを受けました。
乳児の泣き声を気にしたり、妊婦さんが安心して出産することも難しいために、避難所を去っていく乳児の親や、妊産婦さんたち。
その後、避難所に入った職員の報告や東北3県の避難者受入れを通して、文京区の仕組みづくりに向き合いました。
最初はプロジェクトとして、構想を固められたそうですね。
鈴木さん:震災後の課題は山積みでした。
また首都直下型地震がいつ来るともわからない中、新しい予算取りのための資料作成や、審議会等の設置を行っている時間的・労力的余裕はありませんでした。
そこで、任意の(使命感ある地域の人達と)プロジェクトチームを立ち上げました。医師、助産師、看護師など、専門家をはじめ、子育て支援をしているNPOや、地域のパパ・ママにも集まってもらい、昼夜なく知見を集め、「妊産婦・乳児救護所」のプランを練っていきました。
災害弱者の中で、妊産婦と乳児をなぜ重視するのか
壁になったことはありますか?
鈴木さん:社会的弱者と言われる人々(障がい者、高齢者など)の中で「なぜ、妊産婦と乳児を優先するのか」というところでした。
もちろんそれぞれ優先しなくてはなりませんが、東日本大震災の教訓として、特に関心がもたれなかったのが、妊産婦と乳児だと強く感じていました。
そこで、妊産婦等への優先対策の必要性について、いくつもの文献を当たりました。また様々な災害・危機管理の講演会・シンポジウムにも出かけ、エビデンスを集めました。
その中で(当時)東京臨海病院院長山本保博先生からは国際基準では、災害弱者に、
「C(hildren)、W(omen)、A(ged people)、P(atients & poor people)、F(oreingn people)」を
位置付け、対象をとるべきとされていること、その中でもC及びWは妊産婦・乳児をさすと解釈すべきであり、最優先弱者として対策の優先順位を上げなければならない
(『東日本大震災を踏まえた予想される都市災害への医療対応策』と題する講演(2012年8月2日日本危機管理士機構第三講義)と教えられたことは、
その後の対策を進める上で非常に参考になりました
(そのほかにも、スフィア・スタンダードなどもひとつのエビデンス)。
そして、まずは、間違いなく
最優先課題である妊産婦・乳児に対する具体的制度設計を直ちに行おうと考えました
(当時必要性について記述はありましたが、詳細な具体的制度設計については示されたものはなく、
文京区の具体的制度設計はその後、東京都や国にも採り上げられ、全国から問い合わせがあり、
有する地域資源ごとに形を変えて全国に広まっていきました。このことは非常にうれしかったです。)。
国際基準は、災害弱者を以下のように定め、子供・妊産婦を明確に位置付けている。
Children
Women
Aged People
Patients
Poor People
Foreign People
東京臨海病院山本保博院長『東日本大震災を踏まえた予想される都市災害への医療対応策』より
「妊産婦・乳児救護所」の設置場所として、区内の大学と提携したというのも、珍しい取り組み方だと思います。
鈴木さん:避難所としては、小・中学校の体育館が主に指定されています。
ただ、命に関わり、特別な配慮が必要な人達への上乗せ対応として、区内の大学、特に女子大学に協力を仰ぎたいと考えました。
女子トイレの数が確保されているなどの利点がありますし、実習設備としてベッドや入浴施設を兼ね備えている大学や、福祉・介護系をもつ大学は、学生の協力という点でも理解を示してくれました。
もちろん最初から二つ返事というわけにはいかず、大学には何度も足を運び、調整し、協定を結びました。
「どの場所を指定できるのか?」、
「防災無線通信機や備蓄をどこに置いて管理を行うのか?」、
「そのサイクルは?」など、
災害という緊急時の、学業との優先関係や、事故の場合の責任負担など、法的関係を何度も詰めました。
考え方のベースは同じでも、大学ごとに議論すべきポイントは異なりました。
同じように、人の派遣を依頼した東京都助産師会館や東京都助産師会、順天堂大学病院等との間でも、単なる紳士・握手協定ではなく、具体的な課題をクリアしてから協定を結びました。
大学との避難訓練も実施
協定後は訓練などしているのですか?
鈴木さん:上位の地域防災計画や、男女平等条例に書き込み、法的位置付けを明確にし、具体策と連動させました。
災害時、誰がどこの避難所、母子救護所の担当になるのか、職員配置のリストも作成しています。
母子救護所は、その場所で安全に出産できることが必要ですから、担当職員は、妊産婦の理解等の研修を受けています。
出産をサポートする助産師さんにも、母子救護所に駆けつける担当表を求めています。
協定を結んだ4つの大学には、①粉ミルク、②アレルギー用粉ミルク、③紙オムツ、④お産セットなどの備蓄もしています。
備蓄のスペースは基本的に文京区が管理しており、
使用期限になったら入れ替えるなど、定期的に中身のチェックも行っています。
災害時の情報発信などはどのように行われますか?
鈴木さん:防災無線、衛星電話、安心・防災メール、ツイッター等のほか、
文京区では日常的な子育て情報を発信している「きずなメール」を利用して、災害時に有用な情報発信をする予定です。
※ きずなメールについての詳細は以下のとおり
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kosodate/merumaga.html
鈴木さんは現在は、男女協働課長、子供・家庭支援センター課長という立場にいらっしゃいますが。
鈴木さん:いつ来るか分からない災害に備えるには、まさに日頃の制度設計、訓練、意識によります。
今後は、構築した制度をメンテナンスしつつ安定運用・バージョンアップしていくことが大切だと思っています。
私は、男女協働(ジェンダー・人権)セクションと、
子供・家庭支援センターセクションを指揮する責任者として、日々全力で、子供の命を守っております。
====================
2020年03月03日
繋がるワークショップは対話型ワークショップで
ご参加している方にも
お話していただきながら
お互いに【学び会う】コトを
大切にスタートしています。
前回は性教育について
性教育の中でも、相手を大切にしてほしい
そういうキーワードが出てきていましたので
今回はパートナーシップと言う流れになりました
非暴力コミュニケーションNVCの
エンパシーサークルのように
ニーズカードを贈りあう
ワークをしました。
それぞれに感じるコト
受け取るコトが違いながらも
安心安全の空間となりました
ご参加の皆様ありがとうございました!
(やまがた)
次回は
自分を知るワークショップです
詳細 申し込みはこちら
https://smart.reservestock.jp/group_lesson_form/index/51539